企業の防災マニュアルとは?作り方をわかりやすく解説
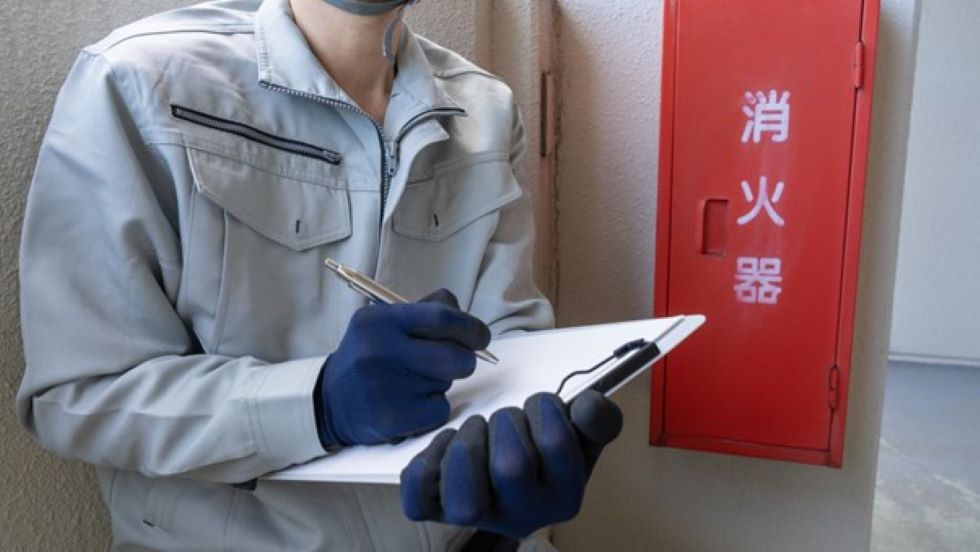
近年、異常気象による自然災害の発生頻度と規模が拡大する中、企業においても人命と財産を守るための徹底した防災対策が求められています。
「防災マニュアル」は、災害発生時の避難方法や役割分担といった情報を従業員が共有し、迅速かつ適切な行動を取るために役立ちます。また、平時から防災マニュアルを用いた防災訓練を積極的に行うことで、いざという時にその効果が最大限に発揮されるでしょう。
今回は、防災マニュアルの役割や作り方、制作のポイントについてご紹介します。
関連記事
企業における防災マニュアルとは?
まず、企業における防災マニュアルの役割とその必要性についてご紹介します。
防災マニュアルの役割
企業における「防災マニュアル」には、自然災害など不測の事態が発生した際に、従業員が取るべき行動がまとめられています。
例えば、災害時の初期対応や避難方法、救助方法、現場指揮者や役割の分担、収集すべき情報とその手段、緊急連絡網についてなどが挙げられます。緊急時の行動指針として活用できるだけでなく、防災訓練を通じて従業員の防災意識を高めるツールとしても有効です。
防災マニュアルの必要性
地震や津波、火災など、自然災害はいつどこで起こるかわかりません。「まさか」という事態が起きた時、従業員個人の判断でやみくもに行動してしまっては組織の統率が取れず、結果として人命や会社の資産を失ってしまう恐れがあります。また、従業員一人の誤った行動が、企業の社会的信頼を大きく損なう可能性もあります。
そこでいざという時を想定した防災マニュアルが従業員に周知されていれば、従業員自身や企業を守るための適切な行動を促すことができます。
防災マニュアルの作り方

防災マニュアルを制作する際には、「役割の明確化」「情報収集」「緊急連絡網」「初期対応・避難体制」といった内容が重要です。各項目を見ていきましょう。
役割を明確にする
災害発生時に自分がどんな役割を果たせばよいのかを把握しておけば、いざという時の行動も自ずと見えてきます。組織全体で速やかに初動対応にあたれるように、役割分担を決めておくことが重要です。
具体的には、災害対策本部を設置し各班を誘導する「統括班」や、情報収集や従業員への食料供給等を行う「総務班」、被災情報の調査・収集にあたる「情報連絡班」、避難時の指揮を担う「避難誘導班」などが挙げられます。
他にも、各班にリーダーを置いて指揮系統を明確にすることや、担当者が不在の場合の代行者も忘れずに決めておくことが大切です。
情報収集の手段と内容を決める
災害時に迅速かつ正確な情報を集められるかどうかも、被害の大きさを左右します。
日常では情報収集の手段としてインターネットや電話、メールなどを用いますが、災害時には通信網が混み合ううえに停電になるなど、スムーズに情報にアクセスできない可能性も高くなります。ラジオや行政の防災無線、災害用伝言サービスなど、複数の情報収集の手段を従業員に周知しておくことが大切です。
加えて、災害時に収集すべき情報の内容についても意識する必要があります。災害発生の混乱時にはデマや不確かな情報が広まることも多々あります。情報の出所を見極めることも大切なポイントです。
緊急連絡網を作成する
緊急連絡網も作成し、防災マニュアルに明記しておくことが重要です。
災害は従業員全員がオフィスにいる間に起こるとは限りません。
外出先や在宅勤務中の従業員の安否確認や被害情報の共有のためにも、スムーズに連絡を取り合えるようにしておく必要があります。
また緊急連絡網は、5人程度の少人数のグループにしておくことがポイントです。これは最初の発信者から最後のメンバーまでできるだけ早く連絡を完了するためです。他にも、1人につき2つ以上の電話番号を登録する、電話とメールなど複数の連絡手段を登録するなども重要です。
また登録した連絡先の情報が変わった場合には速やかに変更届を出すことや、定期的に登録情報の棚卸しを行うこともルール化すると良いでしょう。
初期対応・避難体制を決める
何よりも大切なのは人命です。災害の初期対応として、真っ先に従業員の安全を確保することが求められます。
防災マニュアルには、避難場所への移動タイミングや出火の際の消化手順、負傷者の応急処置についてなど、初期対応時に重要なポイントを誰が見ても瞬時にわかるように明記しておく必要があります。
防災マニュアルを作成するポイント
防災マニュアルを作成する際には、下記のようなポイントをおさえて内容を充実させていきましょう。
人命確保が最優先
避難する際には業務に必要な書類やデータなどを持ち出したくなるところですが、まず最優先すべきは人命確保です。
防災マニュアルでは、「従業員や関係者の命を守ること」を最優先事項として、体制やルールを構築することが重要です。
内容は簡潔・明確に
災害時には、一瞬の判断によって被害の拡大を防げるかどうかが左右されます。そのため、防災マニュアルの内容は「瞬時に正しく理解できること」が重要です。
長い文章や曖昧な表現を避け、簡潔な文章にイラストや写真で視覚的に補足するなど、わかりやすさを念頭に作っていくことがポイントになります。専門的な内容が含まれる場合は用語集を設けて防災訓練時に読むようにするなど、事前に従業員の理解を深めておくと安心です。
定期的に改善・更新する
防災マニュアルの完成度を追求しすぎるあまり、制作に時間がかかり過ぎて頓挫することのないよう注意しましょう。
「災害はいつ起こるかわからない」ことを前提に、まずは作ってみて社内の防災訓練などに活用してみると良いでしょう。そこで得た従業員からの意見やアイデアを反映し、定期的に改善・更新することで、組織全体の防災意識を高めることができます。
これによって一般的な防災マニュアルにはない、自社ならではの対策が見つかるかもしれません。ブラッシュアップを重ねて、より内容を充実させていくことをおすすめします。
関連記事
防災マニュアルの作成と併せて実施したい対策
防災マニュアルを作成するだけでなく、以下の対策を併せて実施することで、災害への備えをさらに万全にすることができます。
BCP(事業継続計画)の策定
災害発生時に、従業員や資産を守りつつ、重要事業を継続・早期復旧させるための計画です。マニュアルが個々の行動指針であるのに対し、BCPは事業全体を守るための経営戦略と位置づけられます。サプライチェーンの寸断や情報システムの停止など、具体的なリスクを想定して対策を講じます。
関連記事
安否確認システムの導入
災害発生直後に、従業員とその家族の安否を迅速かつ確実に確認するためのシステムです。電話やメールが繋がりにくい状況でも、専用のプラットフォームを通じて安否状況を収集・集計できます。これにより、事業の復旧に向けた人員確保の見通しを立てやすくなります。
定期的な防災訓練の実施
マニュアルの内容を従業員に浸透させ、実践できるようにするため、定期的な訓練が不可欠です。避難訓練、初期消火訓練、救護訓練のほか、安否確認システムを用いた情報伝達訓練や、BCPに基づく意思決定訓練(図上訓練)なども有効です。
備蓄品の整備と定期的な見直し
水、食料、簡易トイレ、医薬品といった基本的な備蓄品を、最低でも3日分、推奨として1週間分用意します。従業員の人数や事業所の特性を考慮して、必要な品目と数量をリストアップし、保管場所を定めます。また、定期的に消費期限を確認し、入れ替えを行うことも重要です。
BCPと防災マニュアルの違い
BCP(事業継続計画)と防災マニュアルは、どちらも災害対策の一環ですが、目的や位置づけに違いがあります。
目的の違い
防災マニュアルの主な目的は、災害発生直後の「人命の安全確保」です。避難行動や初期対応など、従業員一人ひとりの命を守る具体的な行動手順が中心です。
一方、BCPの目的は「事業の継続と早期復旧」です。人命の安全確保を大前提としつつ、重要業務をどのように継続し、目標時間内に復旧させるかという経営的な視点での計画となります。
想定する時間軸の違い
防災マニュアルは、主に災害発生の瞬間から数時間〜数日間の「初動対応」を対象としています。混乱の中で、まず何をすべきかを定めています。
それに対しBCPは、発災直後から始まり、数週間、数ヶ月にわたる「復旧・事業再開」までの長期的な時間軸をカバーしています。
対象範囲と内容の違い
防災マニュアルは、全従業員を対象としており、誰が読んでも理解できる具体的な行動が記載されています。
BCPは、主に経営層や各部門の責任者を対象とし、経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)をどの重要業務に優先配分するかという経営判断に関する内容が中心です。
参考になる防災マニュアルの例
自社で防災マニュアルを作成する際に、以下の機関が公開しているテンプレートや事例が参考になります。
中小企業庁のBCP策定ガイドライン
中小企業庁は、企業のBCP(事業継続計画)策定を支援するため、基本的な考え方や具体的な策定手順を示したガイドラインや様式を公開しています。防災マニュアル作成においても、リスクの洗い出しや初動対応計画の部分が非常に参考になります。
東京防災(東京都)
東京都が発行している防災ブック「東京防災」は、一般家庭向けの内容ですが、企業においても非常に有用です。災害発生時の具体的な行動や備蓄品の知識がイラスト付きで分かりやすく解説されており、従業員への防災教育資料としても活用できます。全ページがWebサイトで公開されています。
各自治体が提供する事業所向けマニュアル
多くの市区町村では、地域特性(津波、土砂災害、河川の氾濫など)を考慮した、事業所向けの防災マニュアルの雛形や策定支援ツールを提供しています。自社の所在地を管轄する自治体のホームページを確認することをお勧めします。
企業の防災マニュアルに関するよくある質問
- マニュアルはどのくらいの頻度で見直すべきですか?
-
少なくとも年に1回は定期的な見直しを行うことが推奨されます。また、事業所の移転や組織体制の変更、新たな事業リスクの発生などがあった場合は、その都度見直しが必要です。訓練で見つかった課題を反映させることも重要です。
- 策定したマニュアルを従業員にどうやって周知すればいいですか?
-
全従業員が参加する研修会や説明会を実施するのが効果的です。また、社内ポータルサイトや共有フォルダにデータを保管し、いつでも閲覧できるようにしましょう。冊子として配布し、各部署や個人のデスクに常備することも有効です。定期的な訓練を通じて、内容を繰り返し確認する機会を設けることが最も重要です。
- 在宅勤務(テレワーク)の従業員向けの対策は必要ですか?
-
はい、必要です。在宅勤務者向けの防災マニュアルを別途作成するか、既存のマニュアルに追記することが求められます。自宅での安全確保策、業務データの保護、通信手段の確保、安否確認の方法などを具体的に定めておく必要があります。会社から防災グッズの一部を支給することも検討しましょう。
まとめ
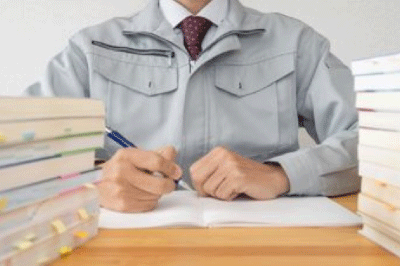
企業が防災マニュアルを定めて従業員に周知することは、企業の社会的責任のひとつです。大切な従業員の命を守るためにも、自社の防災マニュアルを整備しておくことをおすすめします。自社でのマニュアル作成が難しい場合は、専門業者と連携することで、より実用的でわかりやすいマニュアルを効率的に整備することが可能です。
パソナ日本総務部では、マニュアル・取扱説明書制作サービスを提供しています。企画から原稿・図・イラストの作成、印刷までをワンストップで請け負っており、多岐にわたる業界のサービスマニュアルや業務マニュアルにも対応しています。ターゲット視点のわかりやすい表現や、外国語対応などさまざまなご要望にお応えします。
また防災マニュアルの制作だけでなく、防災備蓄品ワンストップサービスでは、防災備蓄品の新規購入・買い替え、在庫管理、棚卸し・リスト化、期限切れ間近の備蓄品回収まで、防災備蓄品に関するあらゆる業務に対応し、最適な防災備蓄品を提案しています。
企業の防災対策にお悩みであれば、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。



