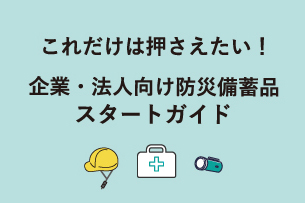BCP訓練とは?種類・進め方・訓練を実施する際のポイントをご紹介

災害などの緊急事態はいつ起こるかわかりません。そのため、事業の継続や早期復旧を目的とした事業継続計画(BCP)の策定は企業にとって欠かせない取り組みです。しかし、計画を作成するだけでは十分とは言えません。実際に訓練を行い計画の実効性を検証することが重要です。
今回は、BCP訓練の目的や種類、実施手順、効果的に進めるためのポイントをご紹介します。
関連記事
BCP訓練とは
BCP訓練とは、災害などの緊急事態が発生した際に事業を中断させないこと、あるいは早期に再開するための「事業継続計画(BCP)」に基づいて実施する訓練です。実際の状況を想定しながら、社員の行動手順や情報伝達の流れ、代替業務体制などを確認・実践することで、計画の有効性を検証し、改善点を洗い出すことができます。
BCP訓練を行う目的
BCP訓練は緊急時に備えて事業継続計画(BCP)を実際に試し、課題を洗い出すための重要な取り組みです。
ここでは、BCP訓練を行う主な目的を3つに分けて紹介します。
従業員に必要な知識を習得させるため
災害などの非常時には、迅速かつ的確な対応が求められます。BCP訓練を通じて従業員が自らの役割や行動手順、連絡体制を実践的に学ぶことで、緊急時に必要な知識と判断力を身につけられます。こうした知識の習得は、混乱の中でも冷静に行動する力を養い、被害の最小化や事業の早期復旧につながります。
防災意識を高めるため
BCP訓練は従業員一人ひとりの防災意識を高めるうえでも重要な役割を果たします。日常業務の中では災害を意識する機会が少ないため、訓練を通じて災害を疑似体験することで、「自分ごと」として捉える意識が育まれます。防災に対する意識が高まれば、いざというときの初動対応の精度が増し、組織全体のリスク対策の質も向上させることが可能です。
BCPの改善につなげるため
BCP訓練は策定した事業継続計画(BCP)の実効性を確認し、改善につなげる上で欠かせません。訓練を実施することで、計画に潜む不備や実際の現場の状況と運用方法の乖離など、想定外の課題が明らかになることがあります。実際に行動してみなければ発見できない問題点を洗い出し、そこから具体的な改善策を検討することが可能です。こうした見直しを繰り返すことで、より現実的かつ実践的なBCPへと進化させることができます。
BCP訓練の種類

BCP訓練と一口に言っても、その内容や目的によってさまざまな種類があります。初動対応を確認するものから、事業継続の実行性を検証するものまで、訓練の方法や規模は企業の体制や課題によって異なります。
ここでは、代表的なBCP訓練の種類をご紹介します。
机上訓練
机上訓練は緊急事態を想定し、実際の行動を伴わずに進めるシミュレーション型の訓練です。資料を使いながら、各部門の対応手順や意思決定の流れを確認し、課題を洗い出します。初動対応の確認や役割の整理に適しており、初めてBCP訓練を導入する企業にも取り入れやすいのが特長です。
パソナ日本総務部が提供する「そなトレ」は、この机上訓練の効果を高めるためのeラーニングプログラムです。教材学習に加え360度VRでの疑似体験、理解度テストの三段階で構成されており、従業員が災害時に必要な判断力や行動力を体系的に身につけられます。また、管理者向けには学習進捗や理解度を“見える化”できる管理機能もあり、効果的な防災教育の実施と継続的な改善を支援します。こうしたプログラムを活用することで、従業員の防災意識向上とBCP体制の強化が期待できます。
安全確保訓練
安全確保訓練は、災害発生時に従業員の安全を守るための初動対応を実践的に確認する訓練です。避難誘導や応急処置、危険箇所の把握を通じて安全に行動するための手順を身につけます。こうした訓練によって、緊急時の混乱を軽減し、被害の拡大を防ぐことにつながります。
安否確認訓練
安否確認訓練は、災害発生時に従業員の安全状況を迅速かつ正確に把握するための訓練です。専用の安否確認システムや連絡網を使って実際に連絡を取り合い、連絡体制の有効性や課題を検証します。訓練を通じて、連絡の遅れや情報の錯綜を防ぎ、緊急時の迅速な対応を可能にします。
代替施設への移転・対応訓練
代替施設への移転・対応訓練は、災害で通常の事業所が使用できなくなった場合に備え、別の施設へ迅速かつ円滑に移転し、事業を継続するための訓練です。移転手順や設備の準備、業務の切り替え方法などを実際に確認し、問題点を洗い出します。この訓練により、緊急時の混乱を最小限に抑え、早期の事業再開を目指すことが可能になります。
バックアップデータ復旧訓練
バックアップデータ復旧訓練は、災害やシステム障害が発生した際に、重要な業務データを迅速かつ安全に復元・復旧するための訓練です。具体的には、バックアップデータの保存場所の確認や取り出し手順の実践、データ復元のプロセスを検証します。訓練の結果をもとに手順を見直し、緊急時の対応力を強化します。これにより、万が一の際にも慌てず確実にデータを復旧し、業務の早期再開を目指せる体制を整えることが可能です。
総合訓練
総合訓練は、机上訓練や安全確保訓練、安否確認訓練など複数の訓練を組み合わせ、実際の災害発生を想定して行う包括的な訓練です。現場での避難行動や代替施設への移転、情報共有の流れなどを実践的に確認し、組織全体の対応力を高めます。複雑なシナリオを通じて課題を洗い出し、BCPの実効性を検証・改善することが目的です。
実施には準備や調整が必要ですが、より実践的で効果的なBCP体制の構築に役立ちます。
BCP訓練を行う際の一般的な流れ
ここでは、BCP訓練を行う際の一般的な流れをご紹介します。
シナリオを作成する
BCP訓練のシナリオには訓練の目的や対象、災害の種類・規模、被害状況などを詳しく設定し、参加者が現実的な状況をイメージしやすくします。これにより、より実践的な対応力を養うことが可能です。シナリオ作成は訓練の成功に欠かせない工程のため、関係部署や専門家と連携して進めることが重要です。
関連記事
BCP訓練を実施する
BCP訓練は、作成したシナリオに基づいて計画的に進めます。参加者は役割分担に従い、想定された災害発生時の対応を実際の行動を通じて確認します。訓練では、情報伝達の流れや連携体制を検証し、問題点や課題を洗い出すことが目的です。実際の動きや意思決定を体験することにより、計画の実効性を高めるとともに、従業員の防災意識や緊急対応力の向上につなげます。
BCP訓練の振り返りを行う
BCP訓練の振り返りは、訓練終了後に必ず実施すべき重要な工程です。訓練中に発見された課題や問題点を共有し、対応の遅れや連携の不備などを具体的に洗い出します。さらに、参加者の意見や感想を収集することで、現場の実情をより正確に把握することが可能になります。
BCP訓練実施に必要なポイント
BCP訓練を効果的に実施するためには、以下のポイントを押さえる必要があります。
従業員にBCP訓練の目的・意味を理解してもらう
BCP訓練を効果的に進めるためには、まず従業員が訓練の目的や意味を正しく理解することが欠かせません。
単なる形式的な作業と捉えず、災害発生時に自分たちの行動が組織の事業継続に直結する重要な役割であることを認識してもらう必要があります。そのために、訓練の背景や意義、期待される成果を分かりやすく伝え、参加者一人ひとりの意識を高める工夫が大切です。
シナリオは具体的な内容にする
BCP訓練を実効性のあるものにするためには、現実に即した具体的なシナリオの設定が不可欠です。
「地震」や「火事」だけの漠然とした想定では、対応の流れや課題が見えにくく、訓練の効果も限定的になります。
地震や水害、システム障害など、自社のリスク特性に応じた災害を想定し、発生時間や被害状況、対応すべき業務などを具体的に描き出すことが大切です。リアリティのあるシナリオが、参加者の当事者意識を高め、実践的な対応力の強化につながります。
訓練後の評価を行う
訓練後の評価はBCP訓練の効果をより高めるために重要です。
どの対応に遅れが生じたのか、連携時の不備などの課題を振り返り、関係者で共有することで改善点が明確になります。あわせて、訓練参加者の意見も収集し、BCPの内容や手順を見直すことで、実際の災害対応に活かせる体制づくりにつながります。
定期的にBCP訓練を実施する
BCP訓練は一度実施しただけでは十分とは言えません。組織の体制や業務内容、従業員の構成は時間の経過とともに変化するため、定期的に訓練を行うことで、最新の状況に即した対応力を維持できます。また、繰り返し訓練を実施することで、従業員の防災意識が定着し、有事の際にも落ち着いて行動できるようになります。
まとめ

BCP訓練は、計画を実践的に検証し改善を重ねていくために欠かせない取り組みです。従業員の意識向上や組織の対応力強化につながるよう、目的を明確にして継続的に取り組むことが重要です。自社に合った訓練を計画的に実施しましょう。
パソナ日本総務部では、企業の防災対策に関してさまざまなサービスをご提供しています。
「防災備蓄品ワンストップサービス」では、有事の初期対応マニュアルの策定をはじめ、BCP対策全般にわたった支援はもちろん、防災備蓄品の新規購入や入れ替え、適切な在庫管理のサポートも承っております。
さらに、「そなトレ」では、CGによるリアルな災害シナリオやVR体験を活用し、効果的なBCP訓練が可能です。この機会に、実践的な訓練手法として導入を検討してみてはいかがでしょうか。