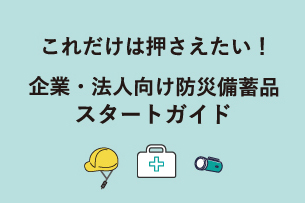介護施設におけるBCPの義務化と具体的な策定方法を解説

2024年4月から、介護施設における事業継続計画(BCP)の策定が義務化されました。これにより、自然災害や感染症発生時にもサービスを中断せずに提供するための体制作りが急務となっています。本記事では、介護施設におけるBCP策定の必要性や具体的な手順などについて詳しく解説します。
介護施設におけるBCP策定の必要性
介護施設においてBCPの策定が必要な理由は、災害や感染症などの緊急事態が発生しても、利用者の安全を確保し介護サービスを継続するためです。高齢者は災害時に特に影響を受けやすいため、平時からの準備が重要です。
BCPの策定により、職員の役割分担や物資の備蓄、情報共有体制を明確にでき、迅速かつ的確な対応が可能になります。介護施設におけるBCP策定は、施設の信頼性向上にもつながる重要な取り組みです。
関連記事
BCPとは
BCPは『Business Continuity Plan』の略で、日本語では『事業継続計画』と言います。BCPは、自然災害や感染症などの緊急事態が発生した際に事業を中断せず、あるいは迅速に復旧させるための計画です。
BCPの主な目的は、事業の重要な機能を維持し、従業員や利用者の安全を確保することです。災害が発生した際にどのように対応すべきか、必要なリソースをどのように調達するか、そしてどのように復旧を進めるかについての具体的な手順を示したものがBCPです。
介護施設においては、利用者の安全を確保するためにも、BCPは欠かせないものです。計画を策定することで、災害時にスムーズな対応が可能となり、事業の中断を最小限に抑えることができます。
関連記事
BCP未策定のリスク
BCPが未策定の場合、介護事業者は重大なリスクを抱えることになります。ここでは「法的罰則」と「事業の安定性の低下」という観点で解説します。
法的罰則
介護事業者がBCPを策定していない場合でも、法的罰則はありません。しかし、BCP未策定の状況は、介護事業者が職員の心身の健康と安全を守るための「安全配慮義務」に違反する恐れがあります。また、労働安全衛生法における罰則の適用や損害賠償請求をされるリスクも考えられます。
また、BCPが未策定のままである場合、介護報酬の減算が適用されます。これらを回避するためには、早急にBCPを策定することが必要でしょう。
事業の安定性の低下
BCPを策定しない場合、自然災害や感染症といった緊急事態が発生した際に、介護サービスの提供が困難になる可能性があります。結果として、事業の安定性が低下し、利用者やその家族からの信頼を失うリスクが高まります。
また、職員の安全が確保できない職場環境では、離職率が上昇する恐れもあります。これらの問題は事業の経営に深刻な影響を与えるため、迅速なBCP策定が求められます。
介護施設におけるBCP策定の基本手順

ここからは、介護施設におけるBCP策定の手順を5つのステップにわけて紹介します。
1. 目的と対応方針の設定
BCP策定の最初のステップは、目的と対応方針の設定です。まず、介護施設がBCPを策定する主な目的を明確化し、具体的な対応方針を設定します。主な目的には、災害時における利用者や職員の安全確保、事業の継続性維持、法令遵守などがあります。
対応方針を設定する際は、各部門の役割分担や緊急時の指揮系統を明確にすることが重要です。これにより、緊急時の混乱を最小限に抑え、効率的な対応が可能となります。また、定期的な訓練や見直しのスケジュールを組み込むことも、重要なポイントです。
2. 重要な業務と資源の特定
2つ目のステップは、重要な業務と資源の特定です。ここで言う重要な業務とは、施設の根幹となる業務を指し、例えば利用者の健康管理業務や食事の提供業務などが挙げられます。また資源とは人材、物資、技術などを指し、その資源が不足すると業務継続が困難となる要素です。
これらを特定することが、緊急時にどのようにして重要な業務を維持し、また資源を確保するのかを検討するベースとなるため、BCPの策定に不可欠なステップです。
3. リスク評価と対策の策定
次に、介護施設で実際に発生しうる、自然災害や感染症などのリスクの種類を特定します。そして、それらリスクの発生頻度や影響度合いを評価していきます。
続いて、発生しうるリスクに対しての具体的な対策を検討します。これらの対策を通じて、介護施設に及ぶリスクを最小限に抑えることが可能になります。
4. 緊急時対応と復旧計画の立案
緊急時対応と復旧計画の立案は、介護施設におけるBCP策定の核心部分です。
まず、緊急時対応計画では、火災や地震といった自然災害や感染症の発生時にどのように対処するかを具体的に定めます。
次に復旧計画ですが、これは、緊急事態発生後に速やかに介護サービスを再開するための計画です。具体的には、被害状況の評価方法と復旧手順を策定します。また、医療機関や自治体との連携を強化し、必要な支援を迅速に受けられるように準備を進めることも重要です。
このように、具体的な対応と復旧の手順を明確にすることで、非常時に迅速かつ適切なアクションを取ることができ、利用者と職員の安全を確保することができます。
関連記事
5. 定期的な訓練と見直し
BCPの効果を最大限に引き出すためには、定期的な訓練と見直しが不可欠です。訓練によって、緊急時における職員の対応力が向上し、実際の災害や感染症発生時にも迅速かつ適切な行動が取れるようになります。そのためには、定期的にシミュレーショントレーニングを行い、実際の現場を想定した実地訓練を実施することが重要です。
また、BCPは一度策定したら終わりではなく、施設を取り巻く環境や状況の変化に応じて見直しを行う必要があります。例えば、施設の設備や運営体制が変わった場合や、新たなリスク要因が発見された場合には、BCPを更新し、その内容を職員に周知徹底することが求められます。
定期的な訓練と見直しを行うことで、介護施設は常に最新のBCPに基づいた体制を維持することができ、利用者や職員に安心と安全を提供することが可能になります。
介護施設におけるBCPの具体例
BCPを策定する際には、「事前に何をしておくか」と「発生時にどのように行動するか」の観点で準備しましょう。ここでは介護施設におけるBCPに取り入れるべき具体例を「自然災害への対策」と「感染症への対策」に分けて紹介します。
自然災害への対策
自然災害対策では、まずハザードマップを活用して地域の災害リスクを把握し、職員と利用者で共有することが重要です。水や食料、医薬品などの備蓄を3日~1週間分用意し、施設の耐震補強や防水対策も進めます。職員には定期的な避難訓練や安否確認訓練を行い、緊急時の連絡網や情報伝達手段を複数整備しておきます。
被災時には、迅速に安否確認や避難誘導を行い、施設被害の状況を速やかに把握できるよう手順などを具体的に定めておきましょう。また、事前に福祉避難所や近隣施設と相互援助の協定を結び、二次避難場所を確保しておくことも重要です。自治体や消防・警察など地域との連携体制を構築し、災害後の早期復旧と事業継続に向けた具体的な計画策定が求められます。
関連記事
感染症への対策
感染症対策では、感染予防マニュアルを整備し、職員への研修を定期的に実施することが必要です。日常的な手洗いやアルコール消毒、マスク着用、換気の徹底に加え、マスクや防護服(PPE)などの衛生用品の備蓄を十分に行います。また、職員や利用者の健康状態を毎日確認し、異常を早期に発見する仕組みを整えましょう。
感染症が流行した際は、面会制限を設けるほか、感染者が発生した場合には迅速な隔離や施設内でのゾーニングを行い、清潔エリアと感染エリアを明確に区分する必要があります。感染者発生時に速やかに対応できるよう、明確な判断基準や対応手順などを定めておきましょう。
そのような緊急時に、利用者の家族に加え保健所や自治体などへの報告を迅速かつ適切に行えるよう役割分担を明確にすることも重要です。
外部リンク
まとめ

2024年4月から義務化された介護施設におけるBCPの策定は、自然災害や感染症の発生時においても、サービスの中断を未然に防ぎ、利用者や職員の安全を確保するために重要です。
パソナ日本総務部では、災害対策やBCP策定の支援など、企業のリスクマネジメントを支援するサービスを提供しています。介護施設のリスク管理体制をより充実させたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。